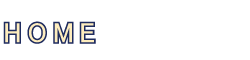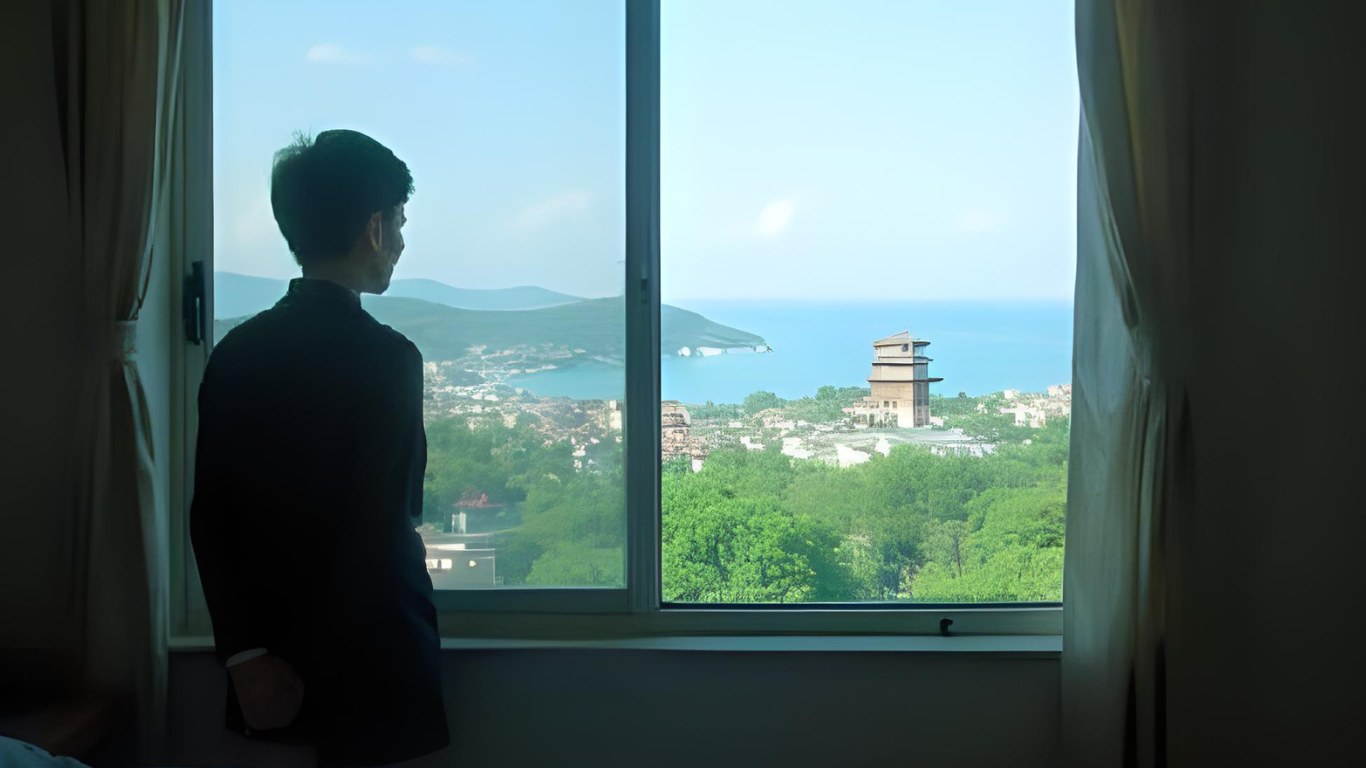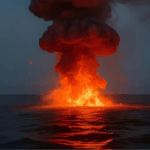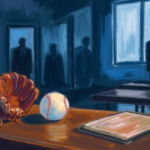日本で「旅行」の経験は、実は年収によって大きく差があることを知っていますか?最近の調査で、日本人の「移動にまつわる格差」がデータではっきりと明らかになりました。
この衝撃的な数字をまずは見てみましょう。過去1年以内に自分の住む都道府県の外へ旅行したことがない人の割合は、年収600万円以上の人では18.2%ですが、年収300万~600万円未満の人だと30.7%、そして年収300万円未満の人ではなんと45.6%にもなるのです。つまり、年収が低いほど、旅行に出かける機会が少なくなる傾向にあることがわかります。この結果は、国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの研究員である伊藤将人氏の著書『移動と階級』で詳しく解説されています。
そもそも、なぜ「移動」がこれほど注目されているのでしょうか。21世紀は「観光の時代」とも言われ、国境を越える観光客は世界中で増え続け、観光産業は大きな成長分野とされています。学問の世界でも、現代社会を理解する上で「観光」や「観光客」という視点が非常に重要だと考えられているのです。資本主義、グローバル化、消費社会、そして「移動」は、まさに現代社会を特徴づける要素がぎゅっと詰まっていると言えるでしょう。実際、世界には推定12億8600万人もの国際観光客がいて、観光産業は世界のGDPの約9~10%を占める巨大な市場です。さらに、新型コロナウイルスの影響で壊滅的な状況に陥った観光業も、今ではほぼ以前の水準まで回復しつつあります。
旅行だけでなく、より長期的な移動である「移民」や「難民」にも目を向けると、その数も膨大です。国際移住者は推定2億8100万人、紛争などで避難を余儀なくされた国内避難民も1億1700万人にも上ると報告されています。そして、移民の経済活動は世界全体のGDPの1割に相当するほどで、これはアメリカや中国に次ぐ規模だと言われています。このように、国境を越える「移動」は、経済的にも社会的にも世界に大きな影響を与えているため、その背景にある格差を考えることの意義はとても大きいのです。
このデータに対し、ネット上ではさまざま意見が出ました。旅行は日々の生活に余裕がないと難しい「贅沢品」だという声が多く、特に「子どもにとって旅の経験は社会の広さを学ぶ上で大切」という意見は、若い方にも響くのではないでしょうか。お金がなくても、時間がなくても、結局は心の余裕がないと旅行は億劫になる、という指摘もありました。一方で、「年収に関係なく、行こうと思えば行ける」「親の価値観やお金の使い方次第」といった声や、「低所得者はそもそも興味の幅が狭い傾向がある」という少し厳しい意見も見られます。
最近では、海外からの観光客(インバウンド)が増え、国内のホテルが高くなり、旅行が一部の人だけの楽しみになりつつあるという現実も指摘されています。また、「旅行はコスパが悪い」と感じる声や「ネットがあれば十分」と考える人もいるようでした。
今回の「移動の格差」というテーマは、単に「旅行に行けるか行けないか」だけの話ではありません。旅がもたらす経験や学び、人との出会い、そしてそれが将来の選択肢や視野にどう影響するのか、という深いつながりがあるように感じられます。経済的な側面はもちろんですが、時間、心の余裕、そして個人の価値観など、さまざま要素が絡み合っている複雑な問題だと言えるでしょう。皆さんの身近でも、このような「移動の格差」を感じることはありますか?
今回は、日本人の移動に関する報道と、それに関するネット上の声をまとめました。皆さんはどのように感じましたか。よかったらコメントをお願いします。