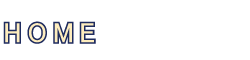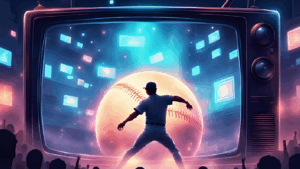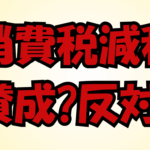最近、日本で起こりうる大規模な災害として、南海トラフ地震と富士山噴火に関する情報が相次いで発表されています。特に、専門家からの強い警鐘や、政府・東京都によるリアルなシミュレーション動画の公開は、わたしたちが直面するかもしれない未来を具体的に示しているものです。
この記事では、これらの重要な情報と、それに対するインターネット上のさまざまな声をまとめました。
「必ず来る」南海トラフ地震と「大地変動の時代」
まず、京都大学名誉教授の鎌田浩毅さん(69)は、2011年の東日本大震災以降を「1000年ぶりの『大地変動の時代』」と表現し、南海トラフ地震について「必ず来る」と強く訴え続けています。政府は「今後30年以内に発生する確率を80%程度」と公表していますが、鎌田さんはさらに踏み込み、「2035年からプラス、マイナス5年で起きる」と、より具体的な時期を予測し、今からの準備を促しています。彼がこのように明確な言葉を使うのは、確率論だけでは人が行動しづらいため、「自分事」として捉えてもらうためだと言います。
南海トラフ地震の震源域は、静岡県沖から宮崎県沖まで約700キロにわたり、「東海」「東南海」「南海」の三つの領域が連なっています。過去の記録を見ると、これらの領域が連動して発生することが多く、例えば江戸時代の宝永噴火の際には三つの領域全てが連動しました。昭和時代には東南海地震の2年後に南海地震が起きています。鎌田さんは、安政時代に三つが連動した後、東海地震が起きていない点に注意を促し、「もう起きないのでは?」と安心せず、次は必ず起きると考えるべきだと述べています。前回から約170年の空白期間があり、1年ごとに「負の利息」がついていると思ってほしい、とも強調しています。
以前には、国が今年3月に南海トラフ地震の被害想定を、そして7月には防災対策をそれぞれ更新しています。これらの動きも、災害への備えが急務であることを示していると言えるでしょう。
富士山噴火シミュレーションが示す首都圏への脅威
次に、富士山噴火についても、内閣府と東京都がシミュレーション動画を公開し、備えを呼びかけています。これは「火山防災の日」(8月26日)に合わせて行われたものです。富士山の最後の噴火は318年前の宝永噴火で、これらの動画ではその宝永噴火と同規模の噴火を想定しているようです。東京大学の藤井敏嗣名誉教授も、「富士山は若い活火山なので必ず噴火する」と警鐘を鳴らしています。
もし富士山が大噴火した場合、さまざまな影響が予想されます。
• 富士山から約100km離れた東京・新宿でも、噴火の2日後には火山灰が5cm以上積もる可能性があります。
• 火山灰は噴火から2時間以内に東京に到達し、健康被害だけでなく、電力供給、交通、食料供給に大きな支障をきたす恐れがあるのです。
• 雨が降ると火山灰が水を吸って重くなり、屋根に30cm以上積もると木造家屋が倒壊する危険性があるとも指摘されています。
• わずか3cmの火山灰でも車の走行が困難になる
• 停電や断水、鉄道の運行停止も広範囲で想定され、噴火から15日目には首都圏全域に火山灰の影響が及ぶ。静岡県内でも、沼津市付近まで停電が広がり、御殿場市周辺では車の走行が不可能になる、といった被害が予測される
• 大規模噴火による経済損失は、最大2兆5000億円と推定される
以前には、東京都が3月に、大規模噴火に備えて住民に2週間分の必需品を備蓄するよう勧告するガイドラインを発表しています。これも、噴火が現実的な脅威として捉えられている証拠と言えますね。
みんなの声とわたしたちの備え
今回の南海トラフ地震と富士山噴火に関する報道に対し、インターネット上ではさまざまな声が上がっています。 多くの人は、もし噴火が起きたら交通機関が止まり、夏の暑さの中で停電したらどうなるのか、という不安を表明していました。また、「2週間分の備蓄で本当に足りるのか」「都市機能が崩壊したら、もっと長期的な避難や国としての対策が必要ではないか」といった、より具体的な疑問や、国策への要望もみられました。中には、「毎年数cmの雪で騒いでいるのに、10cmの火山灰に対応できるはずがない」と、普段の防災意識の低さを指摘する声もありました。一方で、これらの警告が不安を煽ったり、観光客の減少につながるのではないかと懸念する意見も出ています。
これらの声からは、多くの人が災害の現実的な影響を心配していることが分かります。誰にとっても、これらの情報は決して他人事ではありません。いつか必ず来るかもしれない巨大地震と噴火に備え、まずは「自分事」として、家族と話し合ったり、身近な備蓄から始めることが大切だと感じました。
今回は、南海トラフ地震と富士山噴火に関する報道と、それに関するネット上の声をまとめました。皆さんはどのように感じましたか。よかったらコメントをお願いします。