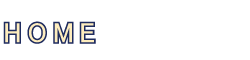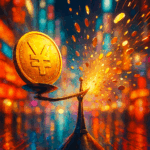自民党と日本維新の会が連立政権を組む上で合意した重要政策に「副首都構想」があります。
この構想の実現に向けて議論が進む中、九州最大の都市である福岡市の高島宗一郎市長が、「首都のバックアップ(予備)機能」という点において、「福岡はまさに適地だ」と名乗りを上げ、大きな話題となっています。
この記事では、副首都構想の基本と、なぜ福岡市が適地だと主張しているのか、そしてネット上の反応をまとめてご紹介します。
副首都構想って何?福岡市長の主張を解説
副首都構想とは、主に「首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築」し、東京に集中しすぎている機能を分散させ、日本全体に多極分散型の経済圏を作ることを目指す政策です。これは日本維新の会の看板政策であり、連立政権の合意書には、2026年の通常国会での法案成立を目指すことが明記されています。
なぜ「副首都」が必要なの?
現代社会では、もし首都・東京で大規模な災害が発生し、国の中心機能が麻痺してしまうと、日本全体が大変なことになってしまいます。そこで、災害や緊急事態が起きた際でも国の機能を維持できるように、あらかじめ「予備」の首都を用意しておこう、というのがこの構想の基本的な考え方です。これをBCP(事業継続計画)の観点と呼びます。
大阪が念頭?そこに福岡市長が待った!
副首都構想は、もともと維新の地盤である大阪での実現が念頭とされていました。
しかし、福岡市の高島市長は10月22日の定例記者会見で、福岡こそが適地であると強くアピールしました。その優位性として、「南海トラフ(地震)の被災リスクが最も少ない」点を強調しています。南海トラフ地震の被害が想定される地域から地理的に離れているため、東京や大阪が同時に被災した場合でも、福岡は機能するという主張です。
高島市長は、副首都の定義(例えば、省庁の移転など統治機構のあり方自体を変えるのかどうか)をしっかり見極めたいとしつつ、BCPの観点から福岡市は非常に適していると重ねて強調しています。
大阪府知事も福岡の可能性に言及
日本維新の会の吉村博文代表(大阪府知事)が、大阪以外にも福岡が副首都になり得るという考えを示していました。
吉村氏は、副首都を担うには、大阪都構想のように政令指定都市と都道府県が一つになる「強力な行政機構」が必要だとして、福岡県と福岡市が都構想の法的根拠である「大都市地域特別区設置法」を活用して一つになれば、ふさわしい都市になると語っています。
ネットの反応・・・議論の中心は「実現性」と「地理的な距離」
この福岡市長の発言に対し、ネット上ではさまざまな意見が飛び交っています。
ネット上では、福岡市長の発言に対し、さまざまな意見が寄せられました。
Yahoo!コメントでは、東京一極集中や南海トラフ地震のリスクを減らすため、福岡が災害に強い「適地」であるという高島市長の主張に「説得力がある」と評価する声が目立ちました。国民としては、災害時に機能する都市が複数あることは安心材料だ、という意見も多く見られます。
しかし、副首都構想の実現には「大都市地域特別区設置法」による特別区の設置が必要となる可能性があり、福岡市と福岡県がこの要件を満たすかどうかといった、制度的な課題が指摘されています。
一方、5ちゃんねるでは、福岡は東京から「遠すぎる」ため、緊急時に陸路で移動できない九州ではなく、中部や関西の方が良いのでは、という指摘がありました。また、福岡は都構想をやる気がないなら候補地として難しいのではないか、といった実現性を問う声も出ています。福岡市民は、首都のバックアップ機能の重要性は理解しつつも、立地や制度上の課題について関心を寄せていることがわかります。
このように、Yahoo!コメントではBCPの観点から福岡の地理的優位性を評価する声が強いのに対し、5ちゃんねるでは地理的な距離や、副首都の前提条件(都構想)を満たせるのかどうかといった実現性の課題を懸念する意見が多く見られる点で、意見の違いが際立っていました。
まとめ
今回の副首都構想は、もし大災害が起きたときに自分たちの生活や社会の仕組みが守られるか、という私たち全員の安心に関わる大切な議論です。また、地方都市が自ら手を挙げて国の重要機能を担おうとする動きは、地方創生のきっかけにもつながるかもしれません。
将来、私たちが住む日本のあり方、そして東京一極集中が本当に是正されるのかどうか、福岡や大阪など、どの都市が選ばれるにせよ、今後の議論を注目していきたいですね。
今回は、副首都構想に関する報道と、それに対するネット上の声をまとめました。皆さんは、副首都はどこが適地だと感じましたか。よかったらコメントをお願いします。